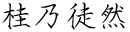30年前のアメリカ紀行備忘録2 『小説アメリカンロード』
2017/04/26
備忘録1では、アメリカを車で旅した話の前振りをして、今後折に触れて書いていくとしたが、帰国した後に書いた短編小説があったことを思い出した 。で、今回はこれを載せてみる。
帰国後、アメリカの旅を、当時の僕は一本の短編小説『アメリカンロード』にまとめている。もうずいぶん昔に廃刊となってしまった近代映画社(映画雑誌『スクリーン』などを発行していた出版社)の、ある雑誌に掲載したのだ。
フリーになりたてでアメリカへ行ったため、帰ってきたらお金がない。とにかく何でもいいから書かせてもらおうと知り合いの編集者に話したら、ノンフィクションではなく小説にしてくれといわれて書いたのが『アメリカンロード』だった。
以下、当時の原稿。
『アメリカンロード』
きっかけは、ファミレスの目玉焼きだった。
気持ち悪いくらいに、どれも同じ大きさで同じ形。ウマイわけじゃないけど、決してマズくはない。
そういえば、八百屋にならんでる大根もきゅうりも、リンゴもナシも、みんな形が整っててウソっぽい。
DCブランドをカタログ通りに着ればどんなヤツもオシャレっぽく見えてしまう。
飲み屋はどこへ行ってもいっしょだし、酒はまがいものばかり。
イイ女が多くなったと思ってたけれど、ちょっと醒めて見てみると、みんな同じ顔、服、体。
キレイで、便利で、そこそこのものが街にあふれている。でも、そのどれもが本物っぽいニセモノばかり。
物に流されているうちに、本物を嗅ぎ分ける力が薄れてきたようだ。昔、駄菓子屋のメンコに一喜一憂したあの貴重な感覚は、まがいものの中で鈍になってしまった。
あーあもうイヤだ!
ウンザリだ!!
仕事を整理するとすぐ、ボクはふらりとアメリカへ飛んだ。
降り立った所は、フェニックス。砂漠の街。この街を旅の起点に選んだのは、ロスやニューヨークに比べて日本人が少なく、イヤ味な東京の雑踏を想像しなくてすむってこともあったけれど、世界で二番目に暑い(ちなみに一番はクウェート)砂漠の荒野に作られた街を見てみたかったことと、友だちの、「あんな暑いだけの街、おもしろくないぜ」という言葉だった。
日本で、東京で、おもしろいと錯覚させられている、薄っぺらな快楽に辟易して飛び出すのだから、反乱するまがいもので人を惑わす所には降りたくなかった。50度を超す灼熱の街、ピュアな砂漠の街、フェニックス。旅のはじめに日本での澱みを殺菌するのにはちょうどいい。
空港でレンタカーを借り一路東へ。旅は始まった。
フェニックスを後にして、40号線をひたすら東へ向かう。さしたるあてもなかったけれど、ただ何となく、西部から南部をぐるっと一周してみようと思っていた。
果てしなく広がる大地と、どこまでも続くハイウェイ。スピードメーターは75〜80マイルを指しているのに、あたりの圧倒的な広さにスピード感を失くしそうになる。どこかの国の名ばかりの高速道路とは大違いだ。
感動的な風景に呑まれていたため、空腹感さえ失せていたのだろう。一日中何も食べていないことに気がついた。急激に押し寄せてきた空腹感に耐え切れずハイウェイを降り、フラッグスタッフという町のはずれにある“COFFE SHOP”という名前の店に入った。
コーヒーショップなのにコーヒーはタダというヘンな店で、ミートボールスパゲッティを頼んだボクは唖然とした。
確かに腹は減っていた。でもこれはないよ。冗談抜きに日本で食べる二食分のスパゲッティに、一個がそのままハンバーグステーキにできるほどボリュームのあるミートボールが、5、6個ぶち込まれている。しかもウマイのだから始末におえない。生粋のヤンキー娘って感じのウエイトレスの屈託のない笑顔に、引きつった笑いで応える酷いジャパニーズという図を地で演じたまま、悪戦苦闘の30分。遂に力つき、半分ほど残してリタイヤ。それにしてもパワーが違う。スケールが違う。
その日泊まったギャロップのモーテルでもまたまたカルチャーショックだ。とにかく部屋が広い。日本のビジネスホテルの三倍はあろうかという部屋で、一泊20ドル(約2600円)。しかもそんなモーテルのほとんどがプール付きなのだ。「スゴイホテルだね」
僕は初老のフロント係、ダン・ブランカに話しかけた。
「ヒドイだろ。安モーテルだからね。悪いけど我慢してくれ」
ダンは明らかに勘違いしているようだった。
「いや、違うんだ。あまりに立派で驚いている」
日本語で書くとカンタンだけれども、英語のできないボクにとって、この言葉を英訳しダンの誤解を解くためには、汗だくでジェスチャーを試みなければならなかった。
「日本人はリッチだって聞いたけど、なぜこんなモーテルに感激するんだい」
誤解が解けたあとも、ダンは不思議そうにしていたが、ボクの方はダンのある行動に不思議さを感じていた。
キャッシュでチェックインするお客に保証金を先払いしてもらうのはよくあることだが、ダンはそのお金と宿泊者カードを重ね、ホチキスでバチバチととめていたのだ。怪訝そうに聞くボクに、さも当然という顔でダンは応えた。
「お金は大切なものだけど、すべてじゃない。しょせん道具さ」
この大らかなラフさ。物事の価値を正しく把握し、自然体で行動する人々。ボクは、当たり前のことにあまりに驚き過ぎている自分に気づき、日本での生活を思い知った。
アリゾナからニューメキシコ、テキサスを過ぎ、オクラホマに着いた所で35号を南下。目的地は、コーパス・クリスティ。
ハイウェイは相変わらず果てしなく、色あざやかなビッグトレーラーが点在する中に混じって、ボクのワインレッドのシェビーはがんばっている。
変化のない広大な荒野。有史以来人間は、道を造ったり、飛行機を飛ばしたりと、セカセカ動き回ってるけど、この景色は何億年も前からずーっとこの景色なんだろう。ひとりそんな感慨にふけっていると、後ろから猛烈な勢いで飛ばしてくるトレーラーが一台、ボクの横を通り過ぎて行った。荒野の風景にも少々飽き、運転にも余裕が出てきていたボクは、久々の刺激に胸躍らせ、トレーラーを追いかけた。メーターは75マイル。トレーラーの横に並び、軽くクラクション。サングラスにアポロキャップ、顔中髭のゴツイドライバーは、親指を立てニヤリと笑った。「GO!」のサインだ。
直線のハイウェイでのミニバトルが始まった。抜きつ抜かれつしながら、そのスピードと緊張感を楽しんでいたが、上り坂にさしかかって、トレーラーが見る見る遅れだしたところで、後ろからリタイヤのホーンが鳴った。ボクは窓を開け、親指を立てて合図をすると、トレーラーの祝福のホーンが再び響いた。
できすぎた映画のワンシーンのような出来事に舞い上がっていたボクは、そのスピードのまま夢心地で疾走し、やめときゃいいのに、前の車を追い越した。いきなり赤いランプの点滅がバックミラーに映った。そう、ハイウェイパトカーだったのだ。トム・クルーズばりの若いハンサムなポリス、ケビン・マニングにゆっくりと説明され、とりあえず15マイルオーバーで80ドル50セント払わなければならないということだけはわかった。
キャッシュをいきなりポリスにつき出すと、ケビンは苦笑して、払う場所は別にあるから後ろについて来いと言う。しかし停まったのは近所のスーパー。さすがアメリカ、個人主義、合理主義、ポリスといえども業務が一段落すれば、連行中であれ自分の夕飯の買い出しを優先させるのかと変に感心していると、ケビンがボクに降りるよう指示する。ボクにも何か飲み物でも買ってくれるのかと呑気なことを考えていたら、なんと罰金はスーパーのレジで払うんだそうだ。さすがにこれには驚いた。犯罪者としての悲壮感も何もあったもんじゃない。近所のスーパーのおばちゃんに「運が悪かったわね」などとなぐさめられ、「いやぁホントに」かなんか言って照れ笑いする様は、あまりにもほのぼのしすぎていた。おまけに、ひと通り書類作成が済むと、ケビンまで明るく話しかけてくる始末。調子に乗って記念撮影までしてしまった。ルールはルールだから罰は罰。でもそれが済めば同じ人間同士。ポリスだからエライとかいう感覚は微塵もない。みんな明るくフレンドリーなのだ。
そんなコーパス・クリスティで一泊し、この世の楽園かと思われるようなサン・アントニオを後にして(ここの話はまた後日…)、最後の目的地、エル・パソへ向かう。
エル・パソは国境の町。15分ほど歩き橋を渡ると、もうそこは、メキシコの街、ファレスだ。
メキシコに近いアメリカと、アメリカに近いメキシコの差なのか、エル・パソは陰気で、ファレスは陽気というイメージを受ける。
ファレスはとにかく活気のある街だ。アメリカを旅して来て、人の思惑の入らない、本来当然あるべき姿の人、物、事に触れることができたけど、ここには、もっとピュアで素朴な感動があった。
町のあちこちにある屋台のタコスは、日本やアメリカで見かけるどのタコスより見栄えが悪く、実際、内臓肉だけというタコスもあるのだから、決して上等とは言えない。でも、一度これを食べたら、もう他のタコスはタコスと呼びたくなくなる。素朴な本物の味は後を引くのだ。
現地の人が行く市場は毎日がお祭りのような活気だ。そこで売買される物は食べ物にしろ飲み物にしろ決して高級なものではない。だけどどことなく懐かしく、ウマイと言わせてしまう。ほとんどが1ドル弱で買えてしまう玩具は、そのどれもが、昔、メンコを手にしたときの感動を呼び戻してくれる。
それらは、懐かしさと思い出を商売とする日本の観光地の“手作り玩具”とは違って、遊ばれるために、必要とされて作られた物。
物はもともと、必要だから人々に欲され、生産売買されてきたはずなのに、日本では、もはや本来の目的は忘れ去られ、消費することを目的とした無意味な大量生産が行われている。そしてボクらはそれらを、流行という言葉に乗せられて、何の疑いもなく受け入れてしまっている。本物を見る目はどんどん濁り、素朴で本来的な物に対する感動はどんどん薄れてしまっているのだ。
帰り際にボクは、何もしないのに小さな箱の中で飛び跳ねる不思議な豆、ジャンピング・ビーンズを買った。その豆の中には、一インチの3/16の小さな虫が入っている。それが本当なのか単なる伝説なのかはわからないが、豆が箱にぶつかるたびに鳴る素朴な音には、なんともいえない心地よさがある。日本に帰っても、この音を聞く度に、本物を感じる心を取り戻すことができそうな、そんな気がした。
関連記事
-

-
長さんの「…なんてな」
踊る大捜査線で、いかりや長介さん扮する和久平八郎が発する「…なんてな」が好きだ …
-

-
去年の新聞のスクラップから(折々のことば)
去年の新聞のスクラップを見ていたら、 こんな記事があった。 まさにその通り!我が …
-

-
親父の言葉2
「節分の、豆まきはおまえらが出てってからやってない。 鬼は外〜で、万が一おまえら …
-

-
『談志の落語』(静山社文庫)
新聞に立川談春さんの記事が載っていた。師匠である故・立川談志は、二人目の父であ …
-

-
『日詩』のまとめ6月1日〜10日分アップしました
日誌ならぬ『日詩』。半年目に突入。今年の梅雨は晴れの日が多いのですが、気分が梅雨 …
-

-
『日詩』8月1日〜10日のおまとめ
いやあ、暑いですねぇ。 でも『日詩』は書いてましたよ〜。 『日詩』ツイッター詩ま …
-

-
日詩 2月1日〜10日(2018)
日詩のまとめです。 日詩(ツイッター詩まとめ) 2月1日〜10日 例えばこんな詩 …
-

-
日詩 9月11日〜20日(2018)
日詩のまとめです。 日詩(ツイッター詩) 9月11日〜20日
-

-
またまた『紅白歌合戦』…そんで、カイト、で岩崎弥太郎と根無し草
皆が「おもしろくなかった」というので、むきになってネタにしているわけではないが …
-

-
『日詩』3月11日〜20日アップ
まだ続いております。日誌ならぬ『日詩』。 毎日ツイッターでせ発信してますが、これ …